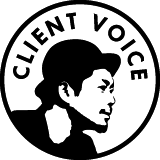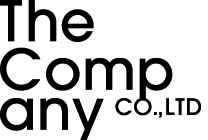Spectator Vol.45「日本のヒッピー・ムーブメント」2020.01.20
半年に一冊のペースで毎回エッヂの効いたテーマを特集する雑誌、スペクテイター。
前回のヒッピー特集に続いて今回は日本のヒッピー特集だ。
あるのかないのか分からない「日本のヒッピー」という不明瞭なムーブメントを戦後の創成期からコミューン解体辺りまで詳細にレポートしている。都市に定着したヒッピー的文化やヒッピー個人の自伝的レポートも掲載していて、一体全体日本のヒッピーとは何だったのかを考える材料を詰め込んだ内容となっている。
大麻、コミューン、農、自然食、精神世界、インド、反戦、サイケデリック、芸術、旅、ラブ&ピース。
ヒッピーとは何で、そして誰なのか。

特集には、私の知り合いの知り合いくらいの繋がりのある人や、行ったことのあるコミューンの祭りが登場する。
ヒッピーカルチャー創成期の人たちはもう70歳かそれ以上になるので本来ならば私とは関わりの少ない人達だ。
しかし、私は目が覚めた時はガイダンスの下にヒッピーの洗礼を受けることが決まっていたようだった。学生時代に農業を経験してみたいと思い、偶然に見つかった近所の農家はドの付くヒッピーだった。親方のアチさんは数十年も前から有機無農薬で多品目の野菜と米を育てていた。脱穀機や農具も昔のものを使っていたり、EM菌を当初から積極的に使っていたりもしていてオタク農家最先端だった。文化、社会運動にも意欲的で、トラックで原発用のウランを載せた車両の行く手を阻んだり、ヤギを連れてデモに参加したりもしていた。
今回のSpectatorにちょこちょこ登場するボブさんがアチさんの家に遊びに来ていたり、詩人の山尾三省さんの追悼記念式の手伝いの仕事を私にさせてくれたりもした。
「名前の無い新聞」という今でも続くヒッピーミニコミ誌やインドの放浪記なんかをくれることもあった。そういった人の繋がりや本なんかが日本のヒッピーの本流であるなんてことは全然思ってもいなかったことで、月日が流れる中でだんだんとその意味が分かる様になっていった。クソガキな私ながらもオールドスクールな「ヒッピー」をリアルに感じることができた、今ではとても貴重な繋がりと時間だった。
今回のspectatorを読むとそんなことをひしひしと感じる。

結果として、今回の特集ではヒッピーとは誰なのかという定義はされていない。
「ヒッピー」とはヒッピーではない人間がそれっぽい人のことを呼ぶために作った呼称であって、自称でヒッピーを名乗る人はいないからだろう。
だから、ふらふらしている私もたまーに、「君はヒッピーだね~」とか言われるのだ。
私はヒッピーなのか・・・。そうなのか・・・。そうなのかもしれない・・・。自分では絶対に言わないけれど。
よく分かっていない人にヒッピーと呼ばれた時はけっこう複雑な心境だ。
それは、私の世界と外の社会とが断絶されて見られているかのような感覚に陥るからだ。
「思想的に、あなたと私は違う」みたいなことを言いつけられているような感覚だ。え?ちょっとそれは勝手に私が感じ過ぎているだけなのかも?ん??分かりませんが。わかんねーけどさ。わかんねーんだよ。

まとまらないとても個人的感想文になってきてしまい恐縮ですが、最後に神崎夢現さんがspectatorに寄稿した「コミューンは僕らの学校だった」からの引用で締めくくらせていただきます。特集のなかでも一番印象的だった一文です。
「現在の日本は、老いも若きも、精神的な老齢化に陥り、経済的低迷が思考のパターン化&ループ化に拍車をかけ、右翼だけでなく、左翼も保守化して偏見にとらわれ、自ら閉塞状況に追い込んでいるように思える。コミューン運動を、過激な左翼運動の末路と言い切ることは簡単かもしれないが、エコロジーやヘルス・ケア&フィットネスなど、時代を先取り、形を変えて我々の様々な生活に影響を与えていることは否定できない。しかし、都市に生きる人々からは表情が失われ、人間性だけは、以前よりも増して奪われている。この状況を破るカギはどこにあるのだろうか?
コミューン運動は、それまでの経済優先の社会の仕組みに疑問を掲げ、自らの新しい仕組みを作ろうとした意欲的な試みだったが、私が“あしっど・かんぱにい”に希望を見出したのは、何よりも非人間的な在り方を否定し、お互いを尊重する姿勢だった。あれから40年が経ち、当時をふりかえってみると、自分の怠慢や身勝手さを棚に上げて劣等感に陥り、親や教師のせいにばかりしていた自分が見えてくる。それもまた非人間的な姿である。多くの者が、都市での快適さを求めながらも、高い物価のなかで金銭的な不自由さを得ているように、新しい社会の仕組みを作ろうという理想を目指しながらも、結局は既成概念の仕組みの一部となってしまった者も多かろう。人間性の回復は、仕組みではなく在り方なのだから、どこに属しているかは関係ない。本当はどこにいてもできることなのだ。」