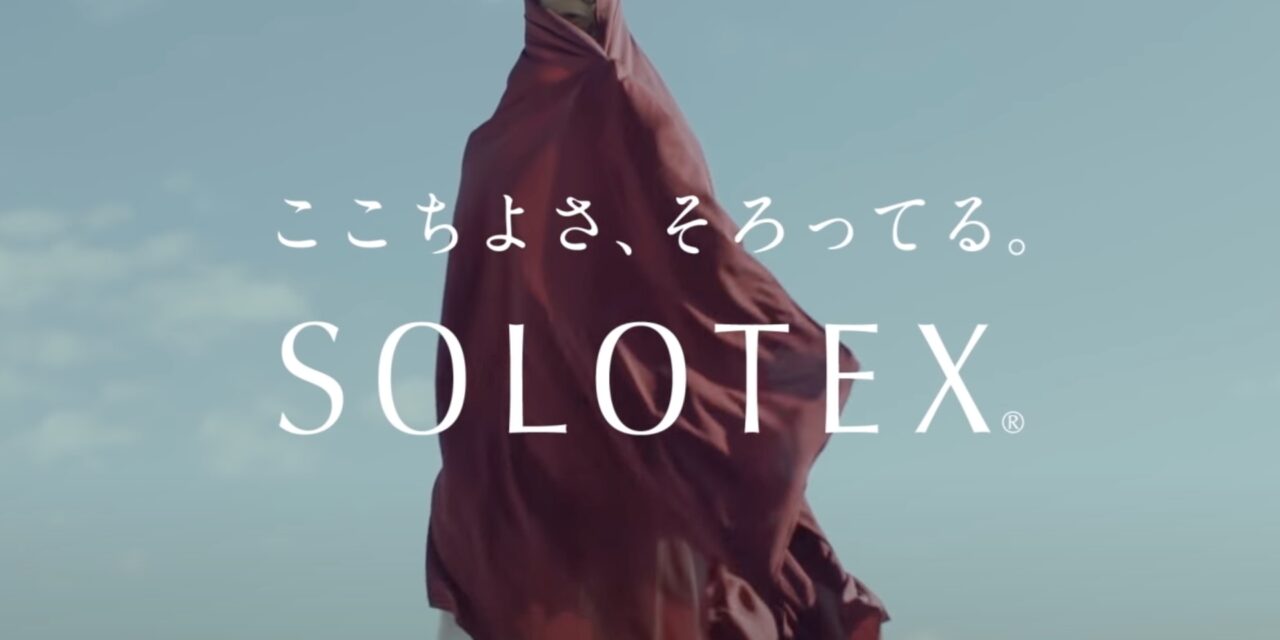Knowledge
2024/07/26
CI・VI・BIの違いとは?ブランド戦略のプロが徹底解説する3つの成功法則
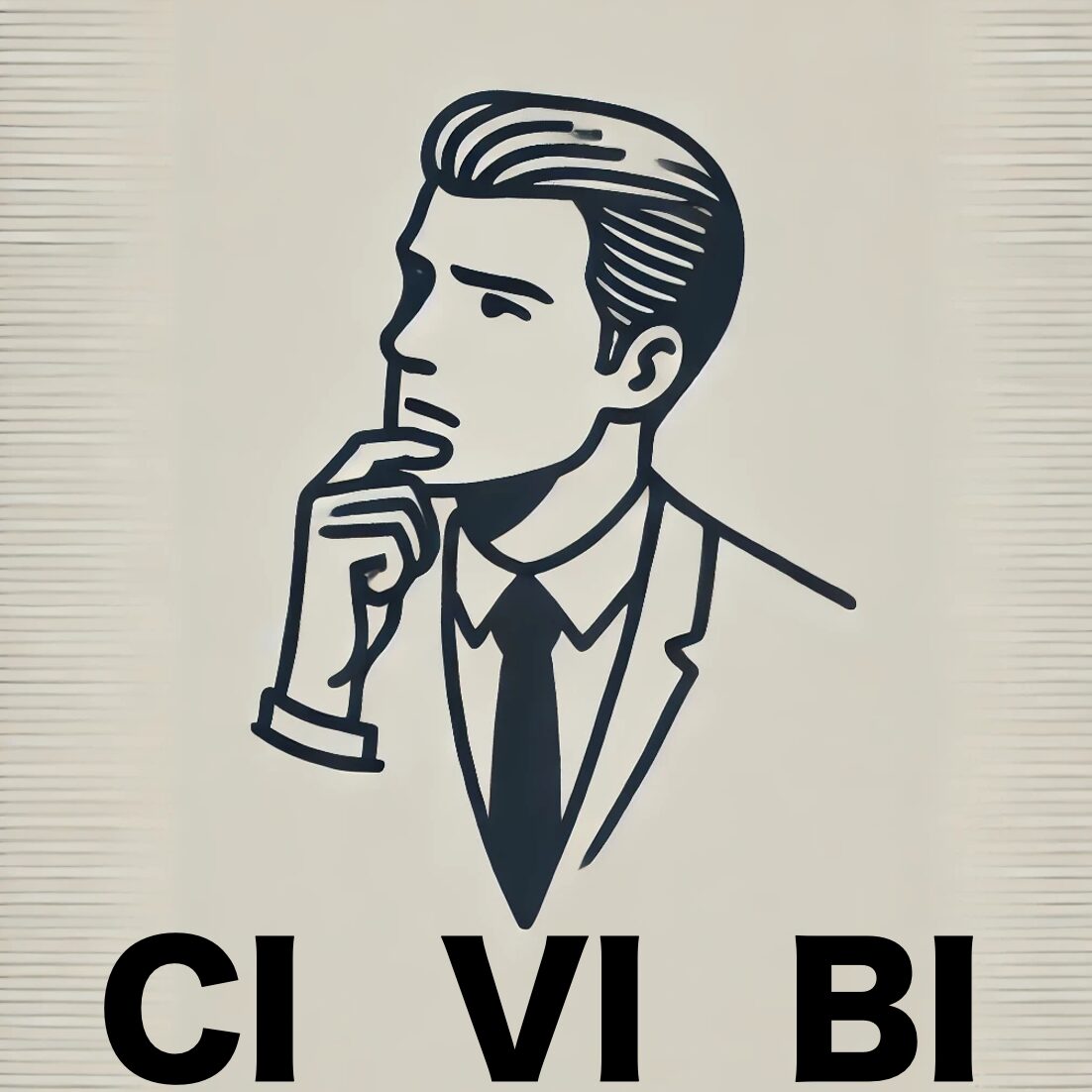
なぜ多くの日本企業がブランディングで苦戦するのか?
実は、多くの企業がCI・VI・BIの違いを明確に理解せずにブランディング施策を進めているのが現状です。「ロゴを変えればブランディング」「見た目を良くすれば売上が上がる」そんな誤解が、ブランド戦略の失敗を招いています。
実際、採用ブランディングに関する調査では、大企業の57.5%が取り組んでいるのに対し、中堅企業は38.4%にとどまるという結果も出ています。 (出典:talentbook株式会社「採用ブランディングにおける取り組み実態調査」2024年2月 )
また、ブランディング経験者の69.3%が「重要性は年々増している」と回答する一方、半数以上の企業が予算・効果測定・相談先などで課題を抱えています。 (出典:ブランディングテクノロジー株式会社「ブランディング意識調査」2022年12月 )
本記事では、ザ・カンパニーが多くのブランディング支援で培った知見を基に、CI・VI・BIの本質的な違いと、実際に成果を上げている戦略的活用法を解説します。読み終える頃には、あなたの企業に最適なブランド戦略が明確になるはずです。
関連Works
1. CI(Corporate Identity)の本質 – 企業の魂を定義する
CIとは何か?その定義と役割
CI(Corporate Identity)は、企業の理念・価値観・ビジョンなど、企業の根幹となる思想体系を指します。単なる理念の羅列ではなく、全ての意思決定の基準となる「企業の魂」そのものです。
一般的にCIは、MI(マインド・アイデンティティ:理念)、BI(ビヘイビア・アイデンティティ:行動)、VI(ビジュアル・アイデンティティ:視覚)の3要素から構成されるとされています。 (出典:ProSharing Consulting「コーポレートアイデンティティ戦略とは?」2023年10月 )
実際、デザイン業界でもCIの解釈は分かれており、「ロゴやマークを指す人もいれば、ブランドステートメントを指す人もいる」という指摘もあります。 (出典:奥野正次郎「BIとCIとVIの違いを考えてみました」note、2021年3月 )
しかし本質的には、CIは企業の存在意義や価値観を体系的に整理したものです。
ちなみに、CIを明確に定義している企業は、そうでない企業と比較して以下のような成果が期待できます:
- 従業員エンゲージメントの大幅な向上
- 離職率の顕著な減少
- 新卒採用応募数の増加
CIが機能する3つの条件
でもなぜ、CIを定めても効果が出ない企業があるのでしょうか?それは以下の3条件を満たしていないからです。
1. 経営陣の本気のコミットメント 形だけのCIでは意味がありません。経営トップが日々の意思決定でCIを体現する必要があります。
2. 社内浸透の仕組み化 策定して終わりではなく、社内ワークショップや評価制度への組み込みなど、継続的な浸透施策が不可欠です。
3. 外部への一貫した発信 社内だけでなく、顧客や社会に向けて一貫したメッセージを発信し続けることで、真のブランド価値が生まれます。
2. VI(Visual Identity)の戦略 – 視覚で伝える企業価値
VIが売上に直結する理由
VI(Visual Identity)は、CIを視覚的に表現するデザインシステム全体を指します。ロゴマークだけでなく、カラーパレット、タイポグラフィ、写真のトーン、空間デザインまで含む包括的な概念です。
実は、統一されたVIを持つ企業は、ブランド認知度が大幅に向上する傾向があります。人間の情報処理の多くは視覚情報に依存するため、VIの重要性は年々高まっています。
成功するVI開発の5ステップ
ステップ1:ブランド診断(目安:2週間) 現状の視覚的要素を全て洗い出し、一貫性をチェック
ステップ2:競合分析(目安:1週間) 業界内でのポジショニングを視覚的に差別化
ステップ3:コンセプト開発(目安:3週間) CIを視覚化するキービジュアルの策定
ステップ4:デザインシステム構築(目安:4週間) ガイドライン作成と全タッチポイントへの展開設計
ステップ5:運用体制の確立(目安:2週間) 社内外のクリエイティブ管理プロセスを標準化
※期間は一般的な目安です。企業規模や要件により変動します。
ザ・カンパニーの実践事例:帝人フロンティア「SOLOTEX®」
弊社が手掛けた帝人フロンティア株式会社の機能素材「SOLOTEX®」のブランディングでは、B2B素材をB2C市場に展開するという難題に挑戦しました。
技術的な機能性を、消費者が直感的に理解できるビジュアルシステムに変換。特に「形態回復性」という難解な特性を、動きのあるビジュアルで表現することで、B2C市場での認知拡大とブランディング強化を実現しました。
3. BI(Brand Identity)の構築 – 顧客との絆を深める
BIが生み出す3つの競争優位性
BI(Brand Identity)は、ブランドの個性・価値観・体験を総合的に定義したものです。CIが企業視点なのに対し、BIは顧客視点でブランドの存在意義を明確化します。
明確なBIを持つブランドは以下の優位性を獲得できます:
1. プレミアム価格の正当化 強いBIを持つブランドは、競合と比較して高い価格設定が可能になる傾向があります
2. 顧客ロイヤリティの向上 リピート購入率の向上やLTV(顧客生涯価値)の増加が期待できます
3. 口コミ効果の最大化 NPS(推奨意向)スコアの向上により、自然な顧客獲得が促進されます
デジタル時代のBI戦略
でも今、BIの在り方は大きく変化しています。Z世代を中心とした新しい消費者層は、ブランドの社会的責任や透明性を重視するようになりました。
実際、日経リサーチの「ブランド戦略サーベイ2024」では、ヤマト運輸が2年連続で総合1位を獲得。「置き配」の本格解禁や協業など、社会課題(2024年問題)に向けた取り組み姿勢が評価されています。 (出典:日経リサーチ「ブランド戦略サーベイ2024総合評価ランキング」)
パーパス(存在意義)の明確化 なぜこのブランドが存在するのか、社会にどんな価値を提供するのかを明確に
サステナビリティへのコミットメント 環境・社会課題への具体的な取り組みをBIに組み込む
コミュニティの形成 顧客を巻き込んだ共創型のブランド体験を設計
4. CI・VI・BIを統合した戦略的ブランディング
PDCAサイクルで進化し続けるブランド戦略
実は、CI・VI・BIは個別に機能するものではありません。相互に連携し、シナジーを生み出すことで真の価値が生まれます。ザ・カンパニーでは、以下のPDCAサイクルでブランド価値を継続的に向上させています。
Plan(戦略立案):目安3-4週間
- 徹底的な対話による本質の探求
- ターゲット分析とペルソナ設計
- ブランドポジショニングの明確化
Do(実行):目安8-12週間
- VI/CI開発とタッチポイント設計
- コミュニケーション施策の展開
- 社内浸透プログラムの実施
Check(効果測定):継続的に実施
- KPI達成度の定量評価
- 顧客反応の定性分析
- 市場ポジションの検証
Act(改善):四半期ごとを推奨
- 成功事例の体系化
- 課題点の特定と対策立案
- 新たな機会領域の発見
※期間は一般的な目安です。プロジェクトの規模や内容により変動します。
Airbnbに学ぶ統合型ブランディングの極意
グローバル企業Airbnbの成功は、CI・VI・BIの完璧な統合にあります。
CI:「誰でもどこでも居場所がある」 単なる宿泊予約サービスではなく、世界中に「居場所」を作るという壮大なビジョン
VI:ロゴ「Bélo」の意味 愛・旅行・居場所を象徴する、シンプルかつ印象的なビジュアルシステム
BI:体験型プログラムの提供 宿泊だけでなく、地元文化や体験を楽しむプログラムで差別化
この3要素が完璧に連携することで、創業から急速に成長し、世界的な企業へと発展を遂げました。
5. 今すぐ始められる!ブランド診断チェックリスト
あなたの企業のブランド力を測る15の質問
以下のチェックリストで、現状のブランド力を診断してみましょう。
【CI診断】
□ 企業理念を全社員が説明できる
□ 理念が日々の意思決定に反映されている
□ 社外への発信が一貫している
□ 理念に基づいた行動指針がある
□ 定期的に理念の浸透度を測定している
【VI診断】
□ ロゴの使用ルールが明文化されている
□ カラーパレットが統一されている
□ 全タッチポイントでデザインが一貫している
□ ブランドガイドラインが存在する
□ VI更新のプロセスが確立されている
【BI診断】
□ ターゲット顧客が明確に定義されている
□ 競合との差別化ポイントが言語化されている
□ ブランド体験が設計されている
□ 顧客からのフィードバックを収集している
□ ブランドストーリーが確立されている
【参考判定基準】
- 10個以上チェック:優れたブランド力を保有
- 5-9個チェック:改善の余地あり
- 4個以下:早急な対策が必要
※この判定基準は一般的な目安です。業界や企業規模により最適なレベルは異なります。
まとめ:ブランド価値を最大化する3つの行動
CI・VI・BIの違いを理解し、戦略的に活用することで、企業のブランド価値は飛躍的に向上します。重要なのは以下の3点です。
1. CIで企業の魂を定義し、全社で共有する 2. VIで視覚的に一貫性を保ち、認知度を高める 3. BIで顧客との絆を深め、ロイヤリティを構築する
ちなみに、ブランディングは一朝一夕には完成しません。しかし、正しい理解と継続的な取り組みにより、必ず成果は現れます。
ザ・カンパニーでは、CI・VI・BI戦略の立案から実行まで、包括的なブランディング支援を行っています。貴社のブランド課題について、ぜひお気軽にご相談ください。
CI・VI・BIに関するよくある質問(FAQ)
Q1. CI・VI・BIの策定にかかる期間と費用はどのくらいですか?
A. 企業規模や要件により大きく異なります。CI・VI・BIの各領域で、期間は数ヶ月から半年以上、費用も数百万円から数千万円まで幅があります。ザ・カンパニーでは統合的なアプローチにより、期間短縮とコスト最適化を実現しています。まずは無料診断で貴社に最適なプランをご提案させていただきます。
Q2. 中小企業でもCI・VI・BIは必要ですか?
A. むしろ中小企業こそブランディングが重要です。限られたリソースで大企業と競争するためには、明確な差別化が不可欠だからです。実際、ブランディング予算を1,000万円以上投資した企業の約半数(49.1%)が増収増益を達成しています。
(出典:タナベコンサルティング「ブランディングに関する企業アンケート調査」2024年10-11月 https://www.tanabeconsulting.co.jp/brand/brandinsight/column/detail85.html)
規模に応じた段階的な導入も可能ですので、まずは最も効果的な領域から始めることをお勧めします。
Q3. リブランディングのタイミングはいつが適切ですか?
A. リブランディングを検討すべき主なタイミングは、①市場環境の大きな変化、②事業領域の拡大や転換、③M&Aや組織再編、④創業から10年以上経過、⑤競合との差別化が困難になった時です。ただし、安易なリブランディングは既存顧客の離反リスクもあります。例えば、ラジオシャックの急激なビジネスモデル変更(2009年)のように、既存顧客層を無視した変更は失敗につながることがあります。
(出典:勝手にマーケティング分析「リブランディング成功事例5選と失敗事例5選」2025年1月 https://marketing-analytics.site/rebranding/)
ザ・カンパニーでは、リスクを最小化しながら効果を最大化する戦略的リブランディングをサポートしています。
Q4. CI・VI・BIの効果測定はどのように行いますか?
A. 効果測定は定量・定性の両面から行います。定量指標としては、ブランド認知度、想起率、NPS(推奨意向)、売上成長率、顧客獲得コスト、LTV(顧客生涯価値)などを測定します。実際、アウターブランディングでは広報・PR活動がブランド価値向上に61.3%の企業で効果を発揮し、インナーブランディングではPMVVの策定が企業文化の強化で61.8%、顧客満足度向上で59.2%の効果が報告されています。
(出典:タナベコンサルティング「ブランディングに関する企業アンケート調査」2024年10-11月 https://www.tanabeconsulting.co.jp/brand/brandinsight/column/detail85.html)
ザ・カンパニーでは独自の測定フレームワークを用いて、投資対効果を可視化しています。
Q5. デジタル時代においてVIはどう変化していますか?
A. デジタル時代のVIは、静的なロゴやカラーだけでなく、動的な要素が重要になっています。モーショングラフィックス、インタラクティブデザイン、レスポンシブロゴ、ダークモード対応など、様々なデジタルタッチポイントでの最適化が求められます。また、SNSでの展開を考慮したマイクロアニメーションや、AR/VRでの表現も検討すべき要素です。ザ・カンパニーは最新のデジタルトレンドを踏まえたVI開発を得意としています。
Q6. ブランディング後の社内浸透はどう進めればよいですか?
A. 社内浸透は成功の鍵となる重要なプロセスです。まず経営層からのメッセージ発信、次に中間管理職への研修、そして全社員参加型のワークショップという段階的アプローチが効果的です。また、日常業務への組み込み(評価制度への反映、社内ツールへの実装など)も不可欠です。ザ・カンパニーでは、企業文化に合わせたカスタマイズされた浸透プログラムを提供し、確実な定着をサポートしています。

相村 満
アートディレクター
新潟県出身。印刷会社、デザイン事務所、広告代理店を経てTCに参加。人の心に響くコミュニケーションデザインを心がけています。