Knowledge
2024/08/09
展示会集客を成功させる完全ガイド|事例で学ぶブースデザインと戦略

展示会の投資対効果で悩んでいませんか?
展示会への出展は、企業にとって大きな投資判断です。ブース設営費、人件費、ノベルティ制作費、運搬費などを合計すると、中規模出展でも数百万円の費用がかかることは珍しくありません。しかし、多くの企業が「本当に効果があったのか」「投資に見合う成果が得られたのか」という疑問を抱えています。
展示会は、顧客と直接対話できる貴重な機会です。オンラインでは伝えきれない製品の質感や、サービスの価値を五感で体験してもらえる場。でもなぜだろう、せっかくの機会を最大限に活かせていない企業が多いように感じます。
本記事では、ザ・カンパニーが実際に手掛けた成功事例を交えながら、展示会で確実に成果を出すための戦略的アプローチを解説します。事前準備から当日の運営、そして事後フォローまで、一貫した戦略によって投資対効果を最大化する方法をご紹介していきます。
成功事例から学ぶ展示会戦略の本質
YDKテクノロジーズ様:国際展示会での戦略的アプローチ
ザ・カンパニーが手掛けたYDKテクノロジーズ様の展示会ブースデザインは、戦略的思考の好例です。ギリシャ・アテネで2年に1度開催される世界最大級の海事展示会「Posidonia 2024」では、製品展示に固執せず、社名と製品認知に絞ったスマートなデザインを採用しました。
展示会の本質は「集客」であるという考えのもと、製品展示に必要なスペースを最小限にすることで来客スペースを最大化。カクテルパーティーという付加価値を提供することで、わずか3時間で約200人もの集客を達成しました。
一方、東京ビッグサイトで開催された「Sea Japan 2024」では、2024〜2025年の2年間を見据えた「機能美」をコンセプトに設計。3面が開放された構造により、「溜まりやすく、流れやすい」空間を創出しました。シンプルで普遍的なモノトーンのデザインは、YDKの信頼された技術力と革新的な姿勢を効果的に表現しています。
東急プラザ銀座様:テーマ性を持たせた空間演出の成功
東急プラザ銀座6Fの「キリコラウンジ」活用プロジェクトでは、単なる展示スペースではなく「ブリティッシュガーデン」というテーマ性のある空間を創出しました。
東急プラザ銀座に多数存在するイギリス初上陸ブランドを巻き込み、著名人によるトークショーや「エドワードグリーンによる革靴のメンテナンス講座」などの体験型コンテンツを展開。ブリティッシュガーデンやコンテンツに興味を持った来場者を各ブランドへ誘導する設計により、**前年同月比売上223%**という驚異的な成果を達成しました。
帝人フロンティア様:バーチャル展示会での新たな挑戦
コロナ禍において、帝人フロンティア様のバーチャル展示会では「現場に来てもらい、実際に商品を観覧することで商談のきっかけを作る」というリアルイベントの強みをWebで再現することに挑戦しました。
展示内容が把握でき、全体が見渡せるパース図をトップページに掲載し、クリック無しで展示のダイジェストが確認可能な仕様として実装。生地のヒキとヨリ、モデルカット(ムービー)を撮影し、実物を手に取った時の感覚に近づける工夫を凝らしました。
実践的ノウハウ:明日から使える展示会成功の法則
事前準備フェーズ:戦略の8割はここで決まる
明確な目標設定の重要性
展示会成功の第一歩は、「なぜ出展するのか」を明確にすることです。新規顧客獲得、ブランド認知度向上、新製品のお披露目、既存顧客との関係強化など、目的によってブースデザインから配布資料、スタッフの対応方法まですべてが変わってきます。
ターゲット顧客の具体的な絞り込み
すべての来場者を狙うのは非効率です。自社にとって最も価値の高い顧客層を明確に定義し、その層に強く訴求するアプローチを設計しましょう。実は、多くの企業がこの段階を曖昧にしたまま出展してしまっています。
ターゲット設定の視点:
- 業界・業種(製造業、IT企業、小売業など)
- 企業規模(大企業、中堅企業、スタートアップ)
- 決裁権限(経営層、管理職、現場担当者)
- 抱えている課題(コスト削減、生産性向上、DX推進など)
デジタル施策による事前集客
展示会の成功は、会場に来る前から始まっています。SNSやメールマーケティングを活用した事前告知により、ブースへの来場を約束する「アポイント」を獲得することが重要です。
ブースデザインフェーズ:3秒で価値を伝える設計
視認性と明確性を両立させる
経済産業省の「展示会産業概論」によると、来場者が1つのブースの前を通過する平均時間は2〜3秒程度とされています。この短時間で「何をしている会社か」「どんな価値を提供できるか」を伝える必要があります。(出典:経済産業省「展示会産業概論」)
YDKテクノロジーズ様の「Marintec China 2023」では、営業部隊が商談しやすいよう、カウンターテーブルとローテーブルのエリアをそれぞれ確保。初公開となる中国語ロゴを隣接するブースとの仕切りを使用させてもらい壁面に大きく掲出することで、遠くからでも視認できるヒキを作る空間設計としました。
体験型展示による記憶定着
見るだけでなく、触れる・試せる・体験できる要素を取り入れることで、来場者の記憶に強く残ります。日産自動車様の「NISSAN CHAYA CAFE」では、サービングロボットとインタラクティブテーブルを導入し、未来のモビリティ体験を効果的に演出しました。
当日運営フェーズ:質の高いリード獲得の仕組み
定期デモンストレーションによる集客
製品の価値を最も効果的に伝えるのは、実際の使用シーンを見せることです。時間を決めて定期的にデモンストレーションを実施することで、人の流れを計画的に作り出せます。
効果的なデモンストレーションのポイント:
- 10分以内でポイントを絞った説明
- ビジュアル重視のストーリーテリング
- 参加型要素の組み込み
- Q&Aタイムの設定
戦略的なノベルティ活用
ちなみに、展示会のノベルティは単なる「お土産」ではありません。ブランド記憶を定着させる重要なツールとして戦略的に活用すべきです。
記憶に残るノベルティの条件:
- 実用性(日常的に使用されるアイテム)
- 独自性(他社にない個性的なデザイン)
- 関連性(自社製品・サービスとの連動)
- 限定性(「会場限定」による価値向上)
事後フォローフェーズ:リードを成約につなげる
データに基づく効果測定
展示会の投資効果を正確に把握するには、事前にKPIを設定し、データを収集・分析することが不可欠です。
重要なKPI指標:
- 来場者数(ブース立ち寄り人数)
- リード獲得数(名刺交換数、アンケート回収数)
- 商談設定数(その場での商談数、後日アポイント数)
- 成約見込み額(パイプライン金額)
迅速かつパーソナライズされたフォローアップ
HubSpot社の調査によると、イベント後5日以内にフォローアップを行った企業は、それ以降にフォローアップを行った企業と比較して、商談化率が約2倍高いという結果が出ています。 (出典:HubSpot “The Ultimate Guide to Event Follow-Up” )
段階的フォローアップの実践:
- 24時間以内:お礼メールと資料送付
- 3日以内:個別の提案内容送付
- 1週間以内:電話でのヒアリング
- 2週間以内:商談日程の確定
まとめ:展示会成功のための3つの重要ポイント
展示会プロモーションで確実に成果を出すための重要ポイントは以下の3つです:
1. 戦略的な事前準備 明確な目標設定とターゲット絞り込みを行い、デジタル施策で事前集客を実施する。展示会の成功は準備段階でほぼ決まります。
2. 体験価値を提供するブースデザイン 3秒で価値が伝わる視認性の高いデザインと、五感に訴える体験型展示で差別化を図る。YDKテクノロジーズ様の事例のように、製品展示だけでなく「集客」を意識した空間設計が重要です。
3. データドリブンな効果測定とフォローアップ KPIを設定してデータを収集し、迅速かつパーソナライズされたフォローアップで、リードを確実に成約へつなげる。
展示会は大きな投資を伴いますが、戦略的なアプローチにより、その効果を最大化することが可能です。単なる「出展」ではなく、事前・当日・事後の一貫した戦略により、確実な成果につなげていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 展示会出展の費用対効果を事前に予測する方法はありますか?
A. はい、過去の実績データと業界特性を考慮することで、ある程度の予測が可能です。まず、過去の展示会での実績(ブース立ち寄り数、商談数、成約数)を分析し、自社の平均的な成果を把握します。次に、出展予定の展示会の規模、来場者層、競合他社の出展状況などを調査し、期待できる来場者数を推定します。重要なのは、定量的な指標(リード獲得数、商談数、成約見込み額)と定性的な効果(ブランド認知度向上、既存顧客との関係強化)の両方を考慮することです。自社の商材単価、成約までのリードタイム、営業体制なども加味して、現実的なROIを試算しましょう。
Q2. 限られた予算で効果的な展示会プロモーションを行うコツは?
A. 予算が限られている場合は、「選択と集中」が鍵となります。まず、ブースサイズを小さくしても、デザインの工夫で存在感を出すことが可能です。縦の空間を活用した立体的なサイン、照明の効果的な使用、シンプルながら印象的なキャッチコピーなどが有効です。また、高額なノベルティよりも、デジタルコンテンツの充実や、SNSを活用した事前・事後のプロモーションに投資する方が費用対効果が高い場合があります。共同出展やパートナー企業との協業も検討しましょう。
Q3. オンライン展示会と対面展示会、どちらを選ぶべきですか?
A. 理想的には両方を組み合わせたハイブリッド型がおすすめです。対面展示会は、製品を実際に体験してもらえる、深い商談ができる、偶発的な出会いがあるという利点があります。一方、オンライン展示会は、地理的制約がない、データ収集が容易、コスト効率が良いという特徴があります。ターゲット層の特性、商材の特徴、予算などを総合的に判断し、必要に応じて両方を活用することで、リーチとエンゲージメントを最大化できます。
Q4. 展示会後のフォローアップで最も重要なポイントは何ですか?
A. 最も重要なのは「スピード」と「パーソナライズ」です。展示会終了後24時間以内に第一報を送ることで、記憶が新鮮なうちにコンタクトできます。その際、単なる定型文ではなく、ブースでの会話内容や相手の課題に言及した個別メッセージを送ることが大切です。また、リードを「今すぐ客」「そのうち客」「情報収集客」などにセグメント化し、それぞれに適したアプローチを行うことで、効率的な営業活動が可能になります。CRMツールの活用も検討しましょう。
Q5. 競合他社が多数出展する展示会で差別化する方法は?
A. 差別化のポイントは「体験価値」と「専門性」です。単に製品を展示するのではなく、来場者が実際に体験できるデモンストレーション、VR/ARを活用した没入型体験、ゲーミフィケーション要素の導入などで記憶に残る体験を提供しましょう。また、特定の業界や課題に特化した専門性の高い展示も効果的です。例えば「製造業のDX」「医療現場の働き方改革」など、具体的なテーマを設定することで、ターゲット顧客により強く訴求できます。事前のSNS発信で話題性を作ることも重要です。
Q6. 展示会スタッフの教育・トレーニングはどのように行うべきですか?
A. 展示会の1〜2週間前から計画的なトレーニングを実施することが重要です。まず、展示会の目的、ターゲット顧客、重点訴求ポイントを全員で共有します。次に、想定される質問と回答例をまとめたQ&A集を作成し、ロールプレイングで実践練習を行います。特に重要なのは、「30秒エレベーターピッチ」と「3分間デモ」を全員が習得することです。また、リード情報の記録方法、優良顧客の見極め方、商談への誘導方法なども統一しておきましょう。当日はシフト制を組み、疲労による対応品質の低下を防ぐことも大切です。

加藤 廉太郎
プロダクションマネージャー
映像会社を経て、ザ・カンパニーに入社。ウェブ、グラフィック、映像、アプリなどのクリエイティブ制作進行を担当。
関連Knowledge
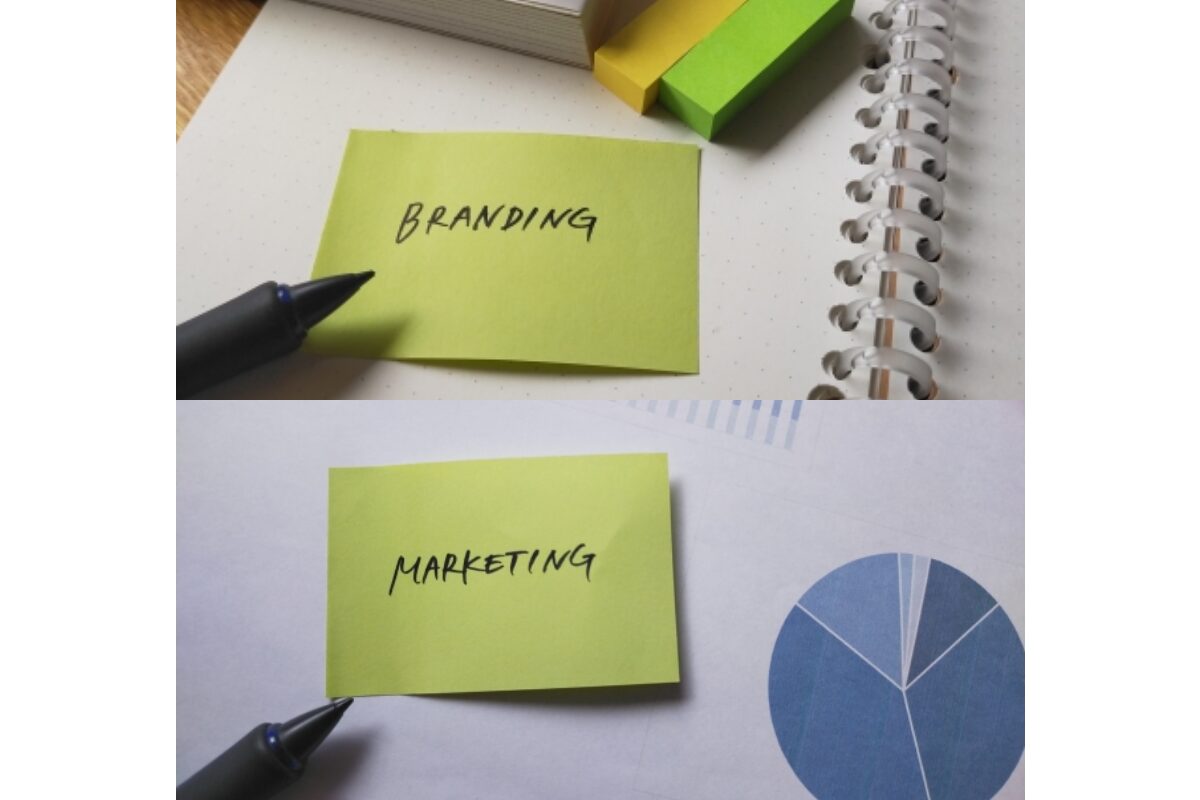 2024
06
27
ブランディングとマーケティングの違いとは?プロが徹底解説する成功への5つのステップ
現代のビジネス環境において、多くの企業が「ブランディング」と「マーケティング」を混同し、効果的な成長戦略を描けずにいます。実は、この2つの違いを正しく理解し、戦略的に連携させることが、価格競争から脱却し、持続的な成長を実現する鍵となります。本記事では、弊社ザ・...
2024
06
27
ブランディングとマーケティングの違いとは?プロが徹底解説する成功への5つのステップ
現代のビジネス環境において、多くの企業が「ブランディング」と「マーケティング」を混同し、効果的な成長戦略を描けずにいます。実は、この2つの違いを正しく理解し、戦略的に連携させることが、価格競争から脱却し、持続的な成長を実現する鍵となります。本記事では、弊社ザ・...
 2024
08
08
ブランドコンセプトとは?プロが徹底解説する成功への3つのステップ
はじめに:なぜ今、ブランドコンセプトが重要なのか
「私たちの会社の強みって、結局何だろう?」「競合と同じような商品なのに、なぜ選ばれないんだろう?」
このような悩みを抱える経営者やマーケターの方が増えています。多くの日本企業...
2024
08
08
ブランドコンセプトとは?プロが徹底解説する成功への3つのステップ
はじめに:なぜ今、ブランドコンセプトが重要なのか
「私たちの会社の強みって、結局何だろう?」「競合と同じような商品なのに、なぜ選ばれないんだろう?」
このような悩みを抱える経営者やマーケターの方が増えています。多くの日本企業...
 2024
06
28
「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」
「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。
本記事では、数多くの企業のブランディ...
2024
06
28
「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」
「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。
本記事では、数多くの企業のブランディ...