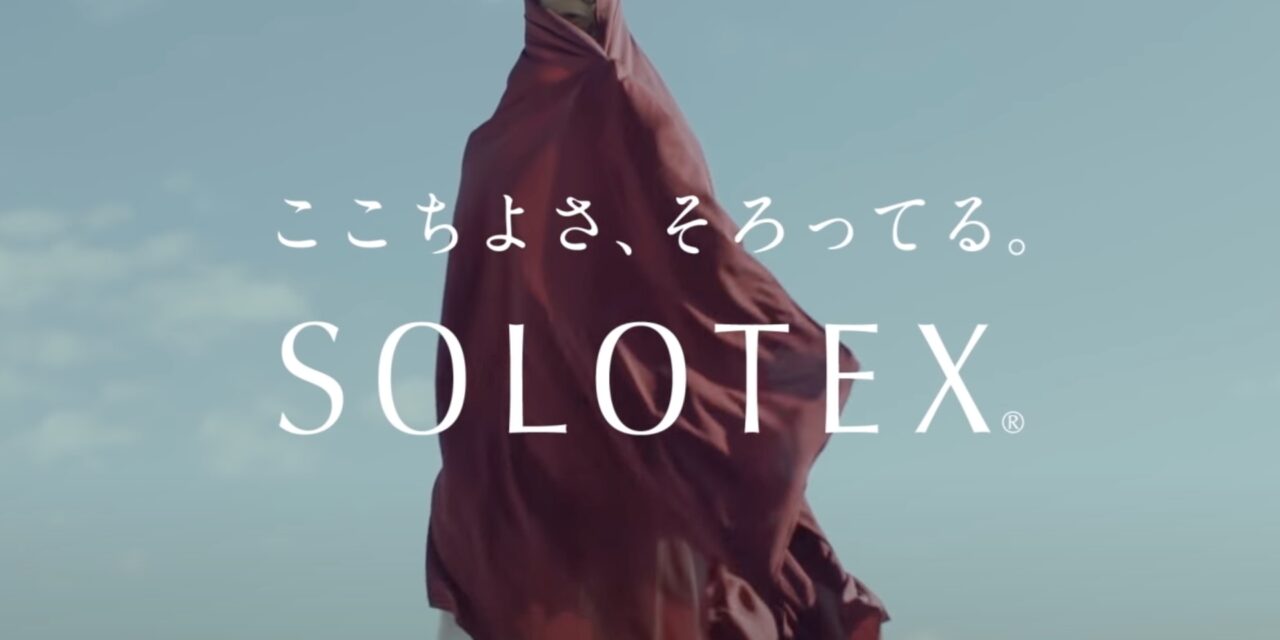Knowledge
2024/08/23
効果的なタグライン開発:ブランドメッセージ戦略の全貌

関連Works
ブランドメッセージとタグラインに関するよくある質問
Q1. ブランドメッセージとタグラインの違いは何ですか?
A. ブランドメッセージは企業の理念や価値観を包括的に表現するものです。一方、タグラインはそのエッセンスを凝縮した短いフレーズ(通常7語以内)です。例えば、Nikeのブランドメッセージは「スポーツを通じて人々の可能性を引き出す」という理念ですが、タグラインは「Just Do It」という3語に集約されています。両者は補完関係にあり、一体となってブランドの価値を伝えます。
Q2. タグライン開発にかかる期間と費用の目安は?
A. 期間は通常2〜3ヶ月程度です。リサーチ・分析に1ヶ月、開発・テストに1ヶ月、最終調整に2〜4週間が標準的なスケジュールです。費用は規模により異なりますが、中小企業で100〜300万円、大企業で500万円以上が相場です。ただし、社内でワークショップを実施すれば費用を抑えることも可能です。投資対効果を考えると、ブランド認知度向上による売上増加で十分に回収できる投資といえます。
Q3. 既存のブランドメッセージを変更するリスクはありますか?
A. 確かにリスクは存在しますが、適切なプロセスを踏めば最小化できます。重要なのは、変更の理由を明確にし、段階的に移行することです。まず社内での浸透を図り、次に主要顧客へ説明し、最後に市場全体へ展開します。無印良品の「これでいい」から「これがいい」への変更のように、ブランドの本質を保ちながら進化させることで、むしろブランド価値を高めることができます。
Q4. B2B企業でもタグラインは必要ですか?
A. B2B企業こそタグラインが重要です。複雑な技術や専門的なサービスを、シンプルに価値を伝える必要があるからです。例えば、弊社が手掛けた帝人フロンティア様の「SOLOTEX®」では、7つの機能を持つ素材の価値を一言で表現することで、B2C市場への展開に成功し、認知度を5倍に向上させました。決裁者の記憶に残るタグラインは、商談の成功率を大きく左右します。
Q5. タグラインの効果はどのように測定すればよいですか?
A. 定量的指標と定性的指標の両面から測定します。定量的には、ブランド想起率(第一想起・純粋想起)、検索ボリューム、SNSでの言及数、Webサイトの滞在時間などを追跡します。定性的には、顧客インタビューやNPS調査で、ブランドに対する印象の変化を把握します。弊社のSync Tankシステムでは、これらの指標をリアルタイムで可視化し、継続的な改善につなげています。
Q6. AIツールを使ったタグライン開発は効果的ですか?
A. AIツールは初期アイデア出しには有効ですが、最終的には人間の感性が不可欠です。ChatGPTなどの生成AIを使って100個以上の案を短時間で生成し、その中から人間が選別・改良するハイブリッドアプローチが効果的です。ただし、AIが生成した案は汎用的になりがちなので、企業の独自性を反映させるには、徹底的な対話と深い理解に基づく人間のクリエイティビティが必要です。弊社では、AIと人間の強みを組み合わせた独自の開発プロセスを採用しています。
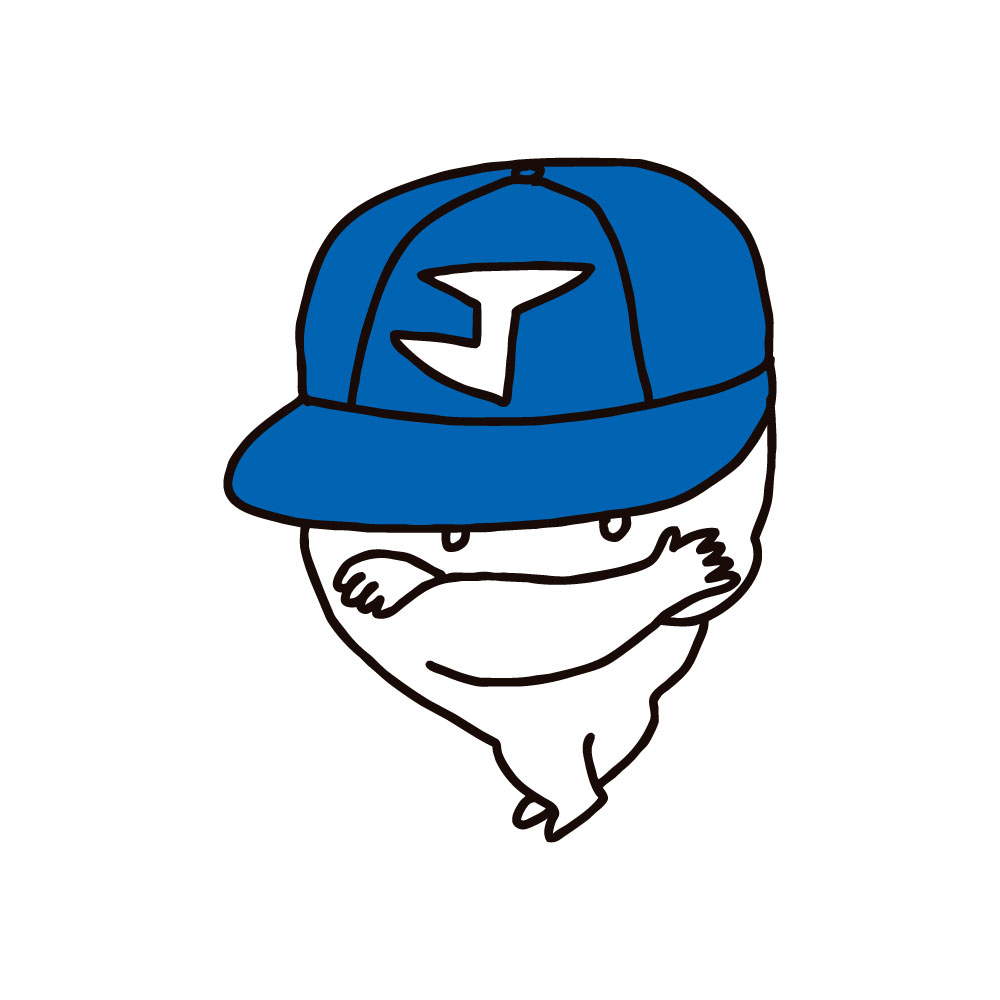
橘 啓介
代表取締役 クリエイティブディレクター
1980年生まれ、東京都出身。2009年にザ・カンパニーを創業。 好きな食べ物:もずく 好きな果物:スイカと梨 好きな薬味:ミョウガとすだち ハマっている漫画:望郷太郎