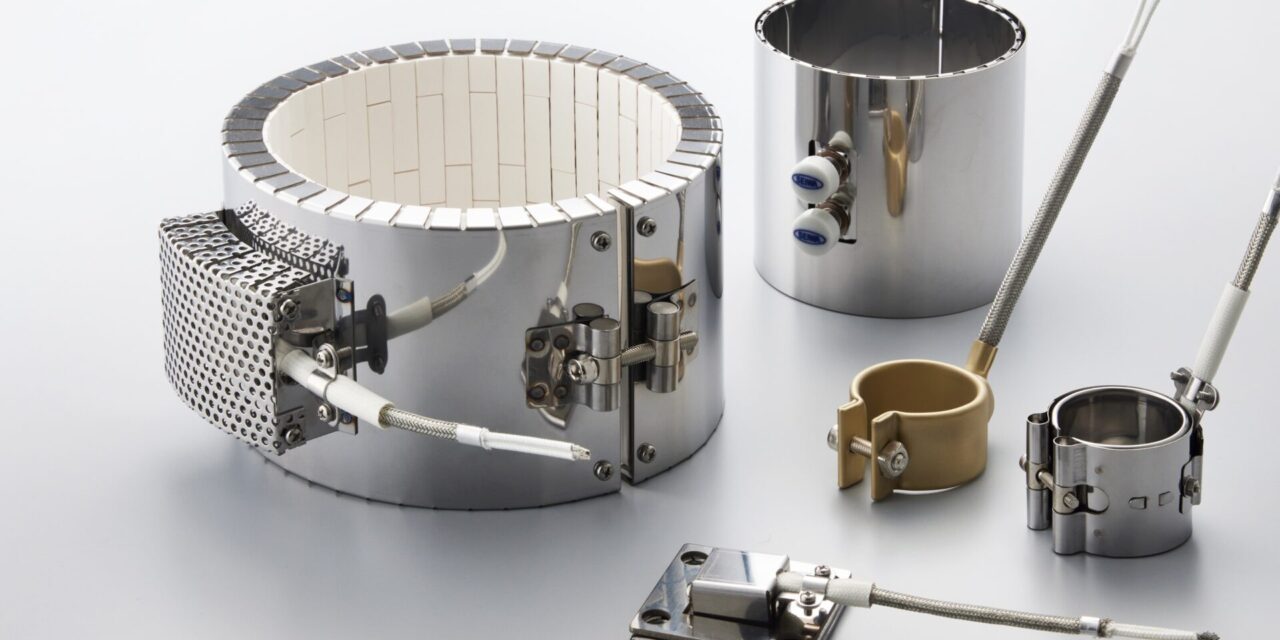Knowledge
2024/08/28
建築・建設業界の本質的ブランディング戦略|価格競争から価値創造への転換

「なぜ、あの建設会社には指名依頼が絶えないのか?」
建築・建設業界で事業を営む経営者なら、誰もが抱く疑問です。技術力や施工品質では負けていないはずなのに、競合他社が大型案件を次々と受注していく。その差を生み出しているのは「ブランド力」です。
弊社ザ・カンパニーが手掛けた大京建機様のブランディング事例では、売上125%向上を実現しました。本記事では、そうした実践経験を踏まえ、建築・建設業界における本質的なブランディングの重要性と実践方法を解説します。
関連Works
建築・建設業界にブランディングが必要な3つの理由
1. 選ばれる理由を作る
建設業界は長年「価格競争」に陥りがちでした。しかし単純な価格競争は利益率を圧迫し、品質維持も困難にします。
**強いブランドを持つ企業は、価格以外の理由で選ばれます。**技術力への信頼、施工品質の安心感、環境への配慮、アフターサービスの充実度。これらの価値を総合的に訴求することで、適正価格での受注が実現します。
2. 信頼関係を構築する
建築プロジェクトは数千万円から数億円規模の投資です。発注者にとって施工会社選びは経営判断そのものであり、実績と信頼性を可視化した「ブランド」が決定的な差を生みます。一貫したブランド体験は、すべての顧客接点で価値を伝え、深い信頼関係を育みます。
3. 長期的な企業価値を高める
強いブランドは環境変化に強く、持続的成長を可能にします。本質的価値に基づくブランド構築により、市場の変動にも揺るがない企業基盤が形成されます。
差別化を実現する5つの戦略ポイント
戦略1|専門領域での圧倒的強みの確立
「なんでもできます」という訴求では、結局何もできない会社と変わりません。成功している建設会社は必ず得意分野を明確化しています。
専門特化の例:
- 医療施設建築のスペシャリスト
- 歴史的建造物の修復・保存技術
- 超高層ビルの特殊施工技術
- 木造建築における伝統技術と現代技術の融合
弊社が支援した企業様でも、特定分野への特化により受注単価を2倍以上向上させた事例があります。
戦略2|DXによる価値の可視化
建設現場のデジタル変革は、単なる効率化ツールではありません。顧客に「この会社は最先端で信頼できる」というブランドイメージを植え付ける重要な要素です。
効果的なDX活用:
- BIMを活用した3D設計提案
- ドローンによる施工進捗の可視化
- VRを使った完成イメージの体験提供
- IoTセンサーによる品質管理データの共有
戦略3|サステナビリティへの本気度
環境配慮は今や必須要素です。表面的な取り組みではなく、数値化された実績と継続的な発信が重要です。
具体的な取り組み:
- CO2排出量の削減目標と実績公開
- 地域産材の積極的活用
- 廃材リサイクル率の向上
- 省エネ建築の標準化
戦略4|人の顔が見える情報発信
建設業は「人」の業界です。職人の技術や想いを可視化することで、信頼感は格段に向上します。
効果的な発信内容:
- 職人インタビュー記事の定期配信
- 現場での工夫や技術をSNSで紹介
- 若手職人の成長ストーリー
- ベテラン職人の技術継承の様子
戦略5|地域コミュニティとの深い関わり
建設業は地域に根ざした産業です。地域との関わりを深めることは、強固なブランド基盤となります。
地元学校での職業体験受け入れ、災害時の迅速な復旧支援活動、地域イベントへの積極的参加など、地域に貢献する姿勢が信頼を生み出します。
ブランディングを成功させる実践プロセス
ステップ1|自社の本質的価値の発掘
ブランディングの第一歩は「自社の強みの言語化」です。多くの企業が「うちには特徴がない」と考えがちですが、長年事業を続けている企業には必ず強みがあります。
強みを発見する3つの視点:
- 顧客視点:なぜ当社を選んでくれたのか
- 競合比較:他社にはない当社の特徴は何か
- 内部視点:社員が誇りに思っていることは何か
過去10年の受注案件分析、リピート顧客へのヒアリング、社員アンケート、協力会社からの評価収集。これらのデータを整理すると、意外な強みが浮かび上がってきます。
ステップ2|ビジュアルアイデンティティの統一
ブランドは「認識の積み重ね」です。ロゴ、色使い、写真のトーンなど、すべての接点で一貫性を保つことが重要です。
統一すべき要素:
- 企業ロゴとその使用ルール
- コーポレートカラー
- 写真撮影のガイドライン
- 文章のトーン&マナー
ステップ3|顧客体験の全体設計
ブランドは広告だけでは作れません。顧客が体験するすべての接点で、一貫した価値を提供する必要があります。
初回問い合わせ時の対応、提案・プレゼンテーション、施工中のコミュニケーション、竣工後のアフターフォロー。各接点での体験を設計し、PDCAサイクルを回すことで、強いブランドが形成されます。
継続的なブランド運用の仕組みづくり
情報発信の継続性確保
ブランディングで最も多い失敗が「始めたけど続かない」です。特に情報発信は、最初の熱意が冷めると更新が止まりがちです。
継続のための仕組み:
- 月1回の定例ミーティングでネタ出し
- 現場写真の撮影ルール策定
- 社員全員が情報提供者になる体制構築
- 外部パートナーとの連携体制
効果測定と改善
「ブランディングは効果が見えにくい」という声をよく聞きますが、適切な指標を設定すれば確実に効果は測定できます。
測定すべきKPI:
- ウェブサイトの訪問者数と滞在時間
- 問い合わせの質の変化
- 指名受注の割合
- 採用応募者の質と量
- メディア掲載数
これらを定期的にモニタリングし、改善を続けることが重要です。
建築・建設業界のブランディング事例
弊社が手掛けた大京建機様のブランディング案件では、創立55年のクレーン業界パイオニア企業の包括的なブランド再構築を実施しました。
各種制作物の個別制作により生じていたブランド統一性の欠如を解決し、企業の核となる価値観を再定義。全コミュニケーションツールに反映させた戦略的リブランディングプロジェクトにより、売上125%向上という成果を達成しました。
Web、映像、グラフィック、パンフレット、サイン、封筒、名刺まで、あらゆるタッチポイントで一貫したブランド体験を設計することで、市場での存在感を大きく向上させることができました。
まとめ:本質的な魅力を引き出すブランディングへ
建築・建設業界におけるブランディングは、もはや「あればいい」ものではなく、生き残りをかけた必須の経営戦略です。
価格競争から脱却し、選ばれ続ける企業になるためには、自社の本質的な「らしさ」を見出し、それを適切に可視化・発信していく必要があります。徹底的な対話による本質の探求、戦略とクリエイティブの融合、そして長期的なパートナーシップによる継続的な改善。これらを着実に実行することで、強いブランドを持つ企業へと成長できます。
建設業界の未来は、本質的な価値を持ち、それを正しく伝えられる企業が切り拓いていくのです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 建設業界でブランディングを始める最適なタイミングはいつですか?
A. 「今すぐ」がベストタイミングです。多くの企業が「まだ早い」と考えているうちに、競合他社との差は広がっていきます。特に創業から10年以上経過している企業や、世代交代を控えている企業は、早急にブランド戦略を見直すことをおすすめします。小さな一歩からでも、継続的な取り組みが大きな差を生み出します。
Q2. ブランディングにかかる費用と期間の目安を教えてください
A. 規模や内容により異なりますが、基本的なブランド戦略策定とVI開発で300万円〜、包括的なブランディングでは1,000万円以上かかることもあります。期間は最短3ヶ月から、本格的な取り組みでは1年以上かかる場合もあります。ただし、段階的に進めることで初期投資を抑えながら効果を確認することも可能です。
Q3. 中小規模の建設会社でもブランディングは効果的ですか?
A. むしろ中小企業こそブランディングが重要です。大手企業と同じ土俵で価格競争するのではなく、独自の強みを明確にすることで差別化が可能になります。地域密着型の強み、専門特化した技術力、きめ細やかな顧客対応など、中小企業ならではの価値を可視化することで、適正価格での受注が実現します。
Q4. ブランディングの効果はどのように測定すればよいですか?
A. 定量的指標と定性的指標の両面から測定します。定量的には、指名受注率の向上、受注単価の上昇、問い合わせ数の増加、採用応募者数の変化などを追跡します。定性的には、顧客満足度調査、従業員のモチベーション向上、メディア露出の質的変化などを評価します。これらを四半期ごとにレビューすることで、投資対効果を明確に把握できます。
Q5. 既存の企業イメージを変えるリブランディングは可能ですか?
A. 十分可能です。実際、弊社が手掛けた事例でも、創業55年の企業が包括的なリブランディングにより売上125%向上を達成しています。重要なのは、企業の本質的な価値を見失わず、時代に合わせた表現方法で発信することです。従業員の理解と協力を得ながら、段階的に変革を進めることで、無理なくイメージ転換が実現できます。
Q6. ブランディングを内製化すべきか、外部委託すべきか迷っています
A. 理想的なのは、戦略立案と基本設計は専門家に委託し、日々の運用は内製化するハイブリッド型です。ブランディングには客観的な視点と専門的な知見が不可欠なため、初期段階では外部の専門家の力を借りることをおすすめします。その後、社内にノウハウを蓄積しながら、徐々に内製化の比率を高めていく方法が最も効果的です。

加藤 廉太郎
プロダクションマネージャー
映像会社を経て、ザ・カンパニーに入社。ウェブ、グラフィック、映像、アプリなどのクリエイティブ制作進行を担当。
関連Knowledge
 2024
10
08
なぜあの企業は選ばれるのか?ブランディングで実現する7つの差別化戦略
実は「ブランディング」で悩んでいませんか?
「良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない」 「競合他社と差別化できない」 「価格競争から抜け出せない」
このような課題を抱える企業経営者やマーケティング担当者の方は多いのではないでしょ...
2024
10
08
なぜあの企業は選ばれるのか?ブランディングで実現する7つの差別化戦略
実は「ブランディング」で悩んでいませんか?
「良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない」 「競合他社と差別化できない」 「価格競争から抜け出せない」
このような課題を抱える企業経営者やマーケティング担当者の方は多いのではないでしょ...
 2024
10
02
選ばれる医療機関になるための医療ブランディング実践ガイド
医療・ヘルスケア業界において、ブランディングは患者との信頼関係を構築する最重要戦略です。
厚生労働省の「令和5年受療行動調査」によると、外来患者の68.4%が「家族・知人・友人の口コミ」から医療機関情報を入手する一方、インターネットで...
2024
10
02
選ばれる医療機関になるための医療ブランディング実践ガイド
医療・ヘルスケア業界において、ブランディングは患者との信頼関係を構築する最重要戦略です。
厚生労働省の「令和5年受療行動調査」によると、外来患者の68.4%が「家族・知人・友人の口コミ」から医療機関情報を入手する一方、インターネットで...
 2024
10
10
【2025年最新】アパレルブランドの成功を導く戦略的ブランディング|実践的7つのステップ
激化するアパレル市場で、なぜ一部のブランドだけが顧客の心を掴み続けているのか。その差を生み出すのは、戦略的なブランディングの有無です。本記事では、ブランドの本質的価値を引き出し、持続的成長を実現するための実践的な方法論を、ザ・カンパニーの豊...
2024
10
10
【2025年最新】アパレルブランドの成功を導く戦略的ブランディング|実践的7つのステップ
激化するアパレル市場で、なぜ一部のブランドだけが顧客の心を掴み続けているのか。その差を生み出すのは、戦略的なブランディングの有無です。本記事では、ブランドの本質的価値を引き出し、持続的成長を実現するための実践的な方法論を、ザ・カンパニーの豊...